対話から始まるキャリア開発 〜カルビーが取り組んだキャリア開発の探究の旅路〜
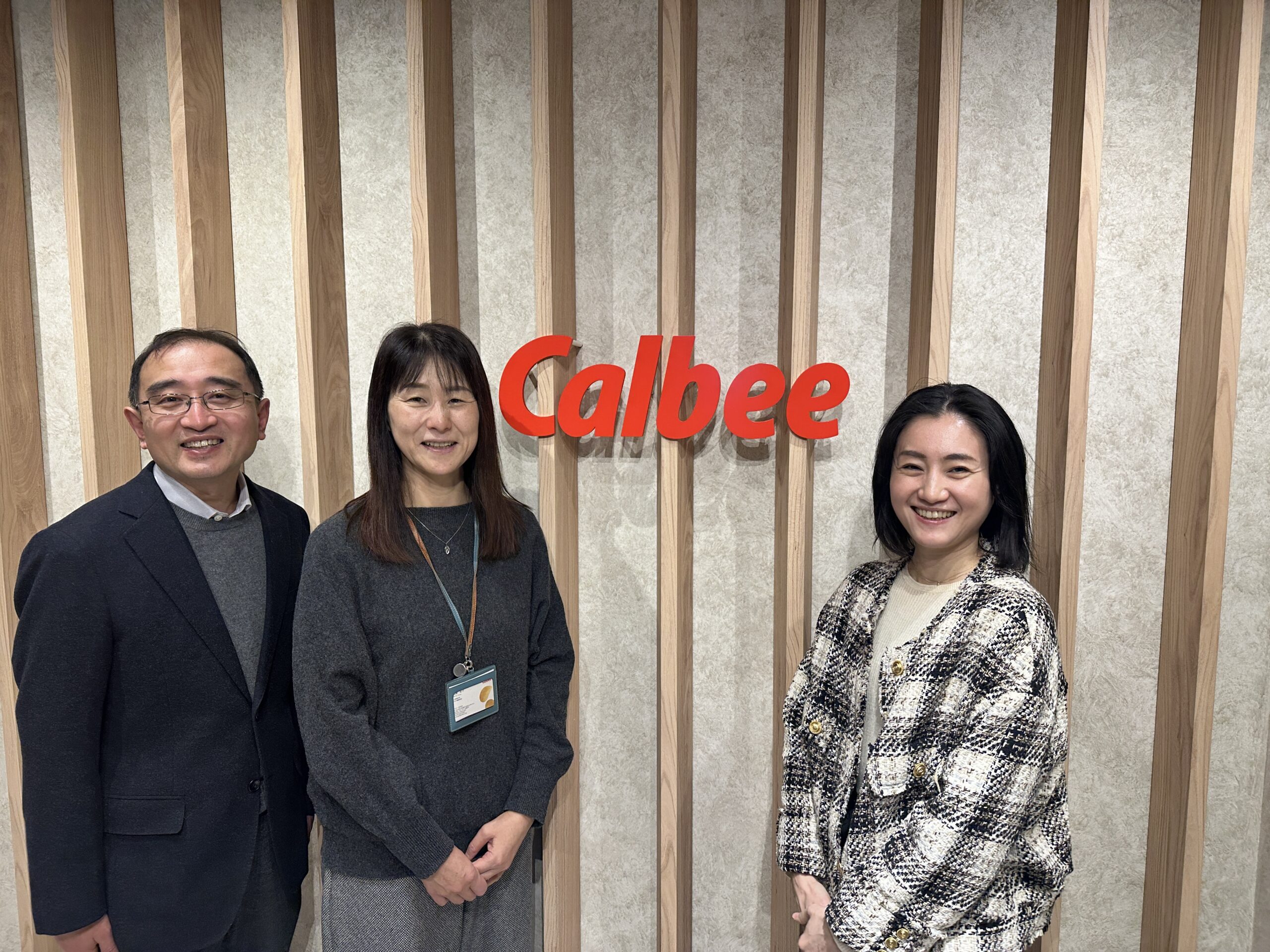
「キャリア開発」は、働く人々のエンゲージメントを高め、成長を促すうえで、多くの企業にとって重要なテーマとなっています。しかし、実際に自社でキャリア開発支援を進めようとした際、あるいは既存の施策を見直そうとする際に、「どこから着手すべきか」「どのように組織に根付かせるか」に悩む企業も少なくありません。
こうした課題に対するヒントを得るため、今回、カルビー株式会社人財戦略部で部長を務める流郷紀子さんにインタビューを行いました。
同社もまた、キャリア開発をどう進めるべきか模索する中で、単なる施策の導入にとどまらず、「カルビーにとってキャリアとは何か?」「キャリア開発は本当に必要なのか?」という根本的な問いを立て、人事部内、そして組織内で対話を重ねながら組織の文化として定着させるプロセスを大切にしてきました。
本インタビューでは、流郷さんとお仲間のみなさまがどのようにキャリア開発を捉え、組織に展開してきたのか、その試行錯誤と探究の旅路をご紹介します。
関連するキーワード
キャリア開発支援の出発点
カルビーがキャリア開発支援に本格的に取り組もうと考えたきっかけはどこにあったのでしょうか?
流郷さん:私自身、組織開発や人財開発に力を入れたいという想いを持って、2021年にカルビーに入社しました。当時のカルビーは、成長の方向性が変化しつつあるタイミングだったと思います。これまでは、強いブランド力の下、努力や工夫を重ねながら、着実に実行することで成果を生み出してきました。しかし、今後はより自発的に行動できる社員が求められると感じていました。
そう考えたとき、キャリアも単に会社から与えられるものではなく、社員一人ひとりが『自分はこうありたい』『こんなことを成し遂げたい』と主体的に考えられるような環境をつくることが重要だと思いました。ちょうどその頃、当時のCHROも“キャリア・オーナーシップ”をキーワードに、会社としてキャリア開発支援を体系化したいと考えていたところでした。 また、入社してすぐに感じたのは、カルビーの社員は本当に素直で良い人が多いということです。社員1人ひとりが、働くことの充実感や手ごたえをより深く感じながら、いきいきと活躍できるにはどうすればいいのか――。そんなことを考えながら、キャリア開発支援の取り組みを進めていきました。

カルビー株式会社 人財戦略部 部長 流郷 紀子さん
問いから始める 〜果たして社員はキャリアをどのように捉えているのだろうか?〜
当時を振り返りながら、スタート時の想いを語る流郷さん。しかし、取り組みを始めるにあたり、そもそも社員がキャリアについてどのように考えているのかが分からず、その点に疑問を抱いていたと言います。
流郷さん:私は中途入社だったこともあり、社内のことが分からない状態でした。「社員の皆さんがどのような思いで働いているのか」「キャリアに対する関心や理解がどれほどあるのか」も全く見えていなかったんです。そこで、まずは現状を把握することから始めようという話になりました。
最初に取り組んだのが、キャリア開発に関するアンケートの実施です。興味深かったのは、「キャリアを明確に描けている人ほど、成長実感が高い」という傾向が非常に顕著に表れたことです。また、「上司からの働きかけが貢献実感に強く影響する」ことも分かりました。
しかし、実態として、自らキャリアを描けている社員はわずか5割程度。さらに、上司が仕事の意義や期待を伝えられている割合も当時は4割にとどまっていました。これは大きな伸びしろがあると感じましたね。
こうした調査結果を社内で共有しながら、キャリア開発が自分たちにとって意義のあるものだと、少しずつ理解を深めていきました。
よりどころを作る:カルビーにとってのキャリアの定義
そして、キャリア開発の実態を理解する上では、アンケートだけでなく、社員の生の声を聞くことも大切にしました。
流郷さん:アンケートの中で座談会の協力者を募ったところ、想像以上に多くの社員が参加してくれました。20代から50代まで幅広い世代の社員が集まり、確か20数回ほど開催したと記憶しています。
座談会を通じて感じたのは、「キャリア」という言葉の捉え方が人によって大きく異なること。そのため、具体的な施策に入る前に、「カルビーにおけるキャリアとは何か? キャリア自律を通じて何を目指したいのか?」 まずは、それを共通言語として定義することが重要だと考えました。
座談会での社員の声を丁寧に読み解き、人事部内でも何度も議論を重ねました。その結果、『キャリア=人生の中で様々な役割を組み合わせ、仕事だけでなく私生活も含めて積み重ねた“自分自身の生涯” そのもの』と定義することにしました。
社員にとって、カルビーでの経験は単に仕事の積み重ねではなく、私生活と密接に結びついたものです。育児や介護、自身の病気など、プライベートの出来事が仕事にも影響を及ぼすことは避けられません。そうした現実を社員一人ひとりが体験しているからこそ、「仕事と私生活は切り離せるものではなく、両方が自分自身を形作るもの」という共通の認識が、座談会を通じた対話の中で深まっていったのです。
こうして、自社におけるキャリアの意味を明確に定義したことは、その後のキャリア開発の取り組みにおいて、大きな指針となり、多様な立場の社員が協働する中で、目指す方向を揃え、迷ったときに立ち戻るよりどころとして機能したと言います。
対話の重要性への気づき、そして書籍との出会い
キャリア座談会を重ねる中で、流郷さんのチームはあらためて「対話」の重要性に気づいたと言います。そこから、書籍『会話から始めるキャリア開発』(ヒューマンバリュー出版)との出会いがありました。
流郷さん:年代別のキャリア座談会を続けるうちに、対話の持つ力を改めて実感しました。いかに対話の機会をつくるか、それがキャリア開発において非常に意義のあることだと感じたんです。
具体的な施策を検討している中で、ヒューマンバリューさんが出版されている書籍『会話から始めるキャリア開発』と出会いました。読んでみると、キャリアにおける「話すこと」の意味や価値を改めて考えさせられました。同時に、カルビーにはこうした対話の文化がまだ十分に根付いていないとも感じました。
しかし、ただ話せばいいというわけではありません。この本には、対話を効果的に機能させるためのヒントが数多く詰まっていました。キャリア開発に向けた具体的な施策を考える上で、チームとして一本筋の通った考えを持ちたいと思い、人事部内で読書会を開くことにしたんです。
ヒューマンバリューさんのホームページには、この書籍を活用した読書会のためのツールが公開されていましたので、それを使いながら、チーム全員で対話の本質を深く考える機会をつくりました。
特に印象に残ったのは、「マネジャーは正解を持っていない」という考え方です。当時、社内では「対話の場を持つ=マネジャーがメンバーを指導すること」や、「キャリアの話をする=異動の約束をすること」と考える人も少なくありませんでした。しかし、この書籍では、マネジャーが答えを持っている必要はなく、むしろ「問いを持たないことが課題である」と指摘されていました。
本当に価値があるのは、対話そのもの。キャリアの方向性を決め、行動するのはマネジャーではなく、本人であるということにあらためて気づきました。読書会を通じた探究を重ねる中で、少しずつマネジャーのあり方について共通の理解が生まれていきました。
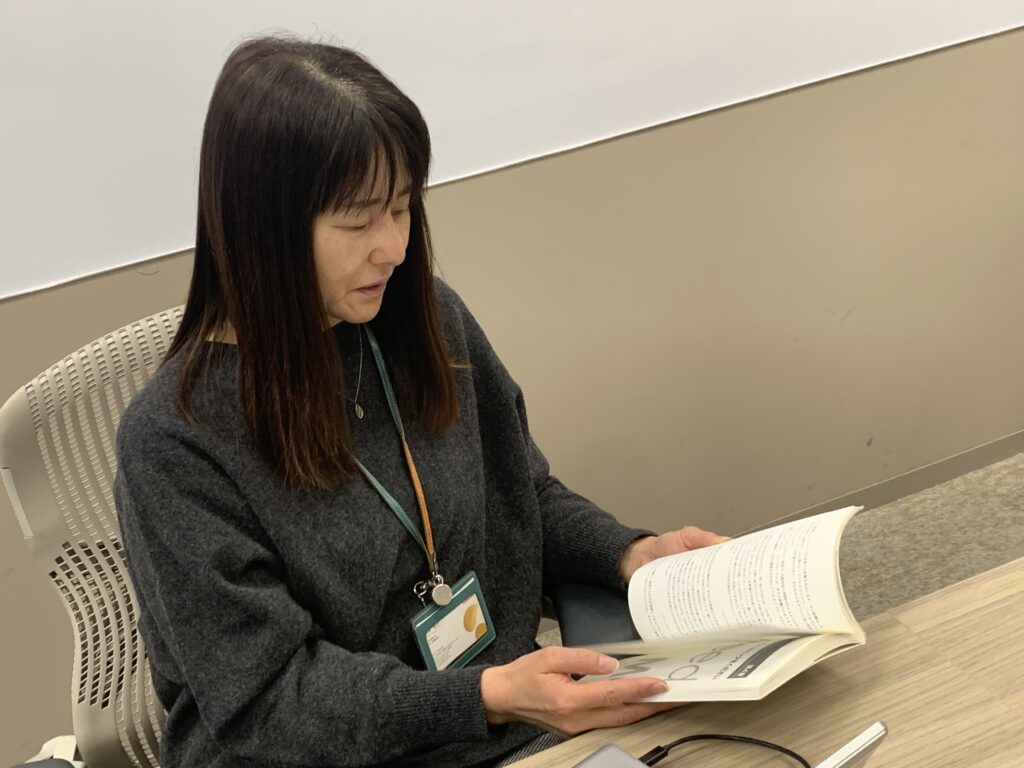
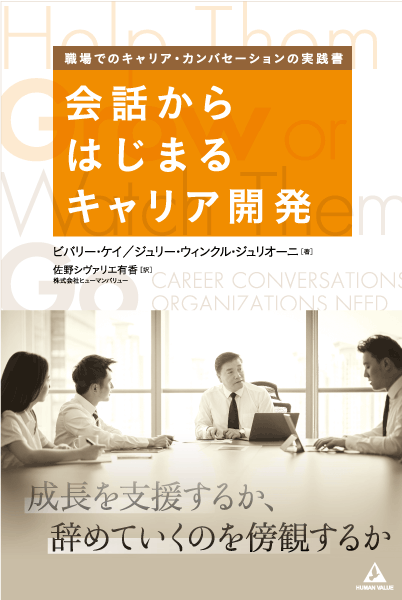
書籍に目を通す流郷さん
キャリアの定義を踏まえたうえで、どのようなアプローチが有効なのかを探るために、人事部内で対話を重ねていったカルビーの皆さま。誰か一人がリードするのではなく、人事部の中でもチームとして取り組める感覚が生まれたと言います。
このように書籍を参考にしながら議論を深めていく姿勢は、まさに『会話から始めるキャリア開発』が目指すものそのものであり、出版に携わった私たちにとっても嬉しい瞬間でした。こうした取り組みそのものが、共有ビジョンを築くプロセスであり、著者であるビバリー・ケイ氏が期待していたことだと感じます。
キャリアの対話を深める「キャリア探究ノート」の誕生
そんな対話の中から、「キャリア探究ノート」の取り組みが生まれてきたのは自然の流れだったのかもしれません。
流郷さん:読書会を通じて、キャリアに関する対話の「質」と「量」を増やすことが重要であるという共通認識が生まれました。その気づきをもとに、社員一人ひとりが自身のキャリアを内省し、マネジャーとの対話を深めるための仕組みとして誕生したのが「キャリア探究ノート」です。
このノートは、単なる異動希望を申告するためのものではありません。「来年どこに異動したいか」ではなく、「中長期的に自分はどうありたいのか、何を目指したいのか」について考え、言葉にすることを目的としています。キャリアとは、本来的には「申請する」ものではなく、自分自身と向き合いながら綴ること自体が重要だからです。
しかし、一人で書くのが難しい人もいるため、上司との対話を通じて思考を整理しながら書き進められるようにしました。つまり、「キャリア探究ノート」は、マネジャーとメンバーのコミュニケーションを促進するツールでもあるのです。ノートの内容も、内省を深め、対話が生まれやすくなるように、書くべき項目の設計にも工夫を重ねました。
これまでにも、部署異動に関する自己申告制度はありましたが、それは人事部に提出するもので、上司との対話を生み出す仕組みにはなっていませんでした。そこで、キャリア開発を本質的に促進するために、「対話を生み出す仕組み」としてこのノートを活用することを決めたのです。
導入に際しては社内でも賛否があり、「上司本人もキャリアを描けていないのに、メンバーにアドバイスなんてできるのか」「異動の決定権を持たないマネジャーが対話をして意味があるのか」といった懸念もありました。しかし、本当の意味でのキャリア自律を実現するには、対話を軸に据えなければならないという強い想いがありました。
そして、「キャリア探究ノート」を導入したことで、マネジャーとメンバーの対話の機会が増えただけでなく、人事部にとっても貴重な情報が蓄積されるようになりました。このノートを通じて得られたデータを基に、人事部は本部ごとに人財育成会議を開催し、異動や育成のあり方をより戦略的に検討できるようになったのです。結果として、メンバー・会社・上司が一体となり、個人のキャリアと会社の成長の双方を支えるマネジメントツール へと発展しました。 このノートが「一過性のものではなく、継続的に活用できる形」にしたのも重要なポイントです。なぜなら、キャリアは「点」ではなく「線」 であり、積み重ねていくものだからです。その意味を込めて「ノート」という名称をメンバーが提案してくれました。
「キャリア探究ノート」の価値や可能性について熱をもって語る流郷さん。導入から3年が経過する中で、今では「キャリ探」と略され、社内で共通言語として受け入れられ、活用されているとのことでした。
次なる展開へ
そして、流郷さんは、キャリア探究の旅路はまだ始まったばかりだと言います。
流郷さん:「キャリア探究ノート」を導入して、まだ3年目ほど。取り組みとしてはまだ十分に定着しているとは言えません。マネジャーとメンバーのキャリア対話が十分に行われていない、という社員も多くいます。まずは、この仕組みをしっかりと社内に根付かせ、推進していくことが大切だと考えています。
また、取り組む中で課題も見えてきました。比較的小規模な部署では機能しやすい仕組みですが、工場などでは一人の上司が多くのメンバーを抱えているため、1対1のキャリア対話の時間を確保するのが難しいケースもあります。また、マネジャーとメンバーの間だけで閉じた対話が本当に最適なのか、という視点もあります。
キャリア対話は、必ずしもマネジャーとの1対1に限定されるものではないはずです。例えば、同じ立場のメンバー同士が互いのキャリアについて話す機会を増やすことで、新たな気づきや学びが生まれる可能性もあります。そういった、新たな対話の形を模索しながら、より開かれたキャリア開発の仕組みをつくっていきたいですね。
「会話から始まるキャリア開発」――その言葉の通り、キャリアは対話を通じて形づくられていきます。対話が増えれば、新たな気づきが生まれ、選択肢が広がり、未来への可能性が拓けていくでしょう。これからの進化が楽しみになるインタビューでした。
最後に、インタビュアーを務めたヒューマンバリューの2人からも、特に大切だと感じた視点や得られた洞察を共有してみたいと思います。
市村絵里
新しい技術が生まれ、女性の社会進出が進み、平均寿命が伸び、終身雇用制度の維持が難しくなっているなど「キャリア」を取り巻く環境が大きく変化している昨今、「キャリア」の育み方や企業の「キャリア開発」のあり方も、時代に合わせて進化する必要性が高まっているのではないかと思います。
一方で「キャリア」という言葉は、一般的な概念として多くの方に浸透している言葉であり、一人ひとりがそれぞれに自分の「キャリア観」というものも持っているのではないでしょうか。そうしたすでに多くの方に浸透している言葉こそ、それぞれの持っているイメージや、言葉の意味のズレを明らかにして、そのズレを解消していくことの難易度は高くなります。
カルビーさんの今回の取り組みでは、そうした認知のズレを解消していくだけではなく、新しい意味を共通理解として生み出していく、丁寧なプロセスを歩まれていることが印象的でした。
そのプロセスの中で、私自身も出版に携わらせていただいた書籍「会話から始まるキャリア開発」を活用いただけたことは、とても嬉しかったです。読書会は、すでにある会議体の一部を使いながら、数回に分けて実施されたということをお伺いし、無理なくできるところから取り組みを始めることで、変化の種を生み出していらっしゃったように感じました。
そして、人事部の中で「キャリア」についての新しい捉え方の共通理解を生み出すことを1つの起点にしたことで、担当者が違う異なる取り組みの中でも、同じ方向を目指した取り組みが生み出され、相乗効果が生まれているように感じました。
そうした丁寧なプロセスを歩まれている背景には、取り組みを通して一緒に働く一人ひとりが「働くことの充実感や手ごたえをより深く感じながら、いきいきと活躍できるにはどうすればいいのか」という大切にしたい想いや願い、芯となるビジョンを持っていらっしゃっていることが大きいのではないかと思います。 流郷さんが語ってくださった想いは、私がお仕事をする中で大事にしたいこととも重なり、とても温かい気持ちになると共に、私自身もプロジェクトで「キャリア」の取り組みをご支援するときに、大事にしたい想いを再確認させていただく機会となりました。
川口大輔
「キャリア開発という言葉が広すぎて、どこから何を始めていいかがわからない。」そんな声を聞く機会が増えてきました。そうした声に対して、カルビーさんの取り組みは、まず「自分たちにとっての意味を対話し、定義するところから始める」という明確な指針を示して下さったように思います。
ヒューマンバリューでは、「共創によるキャリア開発(Co-Creation Career)」という考え方を提唱・実践していますが、そこでは、メンバー、マネジャー、組織(人事を含む)が双方向の対話を通して、これまでの外的・計画的なキャリア観から、内的・生成的なキャリア観へと枠組みをシフトしていくことを目指しています。
カルビーさんの取り組みは、まさに対話を軸にしたCo-Creation Careerであり、こうした枠組みの変化を集合的に起こしていくことが、本当の意味でのキャリア自律やキャリア・オーナーシップを実現する鍵であると感じました。
カルビーさんの挑戦は、これからも続いていきます。マネジャーとの1対1の対話に捉われない柔軟なキャリア・カンバセーションの可能性が広がることを期待するとともに、私たちヒューマンバリューにおいてもそうした共創によるキャリア開発の実現に貢献していきたいと思います。

