System Thinking in Action 2002
関連するキーワード
System Thinking in Actionについて
System Thinking in Actionとは、書籍”The Fifth Discipline”の著者Peter Sengeの提唱するラーニング・オーガニゼーションに関する様々な組織の取り組みや新しい考え方をシェアする場として、1990年よりスタートした国際カンファレンスである(「システム・シンキング」は、そのラーニング・オーガニゼーションを実現するために必要な5つのDisciplineのうち、最も重要で基本となる5つ目のDisciplineである)。
このカンファレンスの主催者は、システム・シンキングに関するテキストや機関誌を発行しているペガサス・コミュニケーションズ社である。例年、同カンファレンスにおいては、ラーニング・オーガニゼーションを研究するリサーチャーやコンサルタント、また導入企業や組織の推進者が集まり、その実践例や具体的な効果、問題点などについて活発なダイアログが行われている。
今回もSystem Thinking in Action 2002が、2002年9月30日~10月2日の3日間、米国カリフォルニア州サンディエゴ市のシェラトン・サンディエゴ・アンド・マリーナにて行われた。今回で12回目を向かえる同カンファレンスに、世界各国から、約700名の参加者が、30を超えるセッションやワークショップに参加した。
ヒューマンバリューからも、同カンファレンスに2名が参加し、多くのセッションへの参加や、各国からの参加者とのダイアログを通して、ラーニング・オーガニゼーションに関する最新動向を把握することができたので、本レポートに報告することにする。
カンファレンスの概要
カンファレンスの構成
System Thinking in Action 2002カンファレンスの構成は以下のとおりであった。
1. Plenary Session(基調講演)
本年度は以下の8人により、7つの基調講演が行われた
・Breakthrough Groupの創設者、Mitch Litrofsky
・Whole Systems Associatesの創設者、Juanita Brown
・GMのStrategic Initiativeのディレクター、Nick Pudar
・Illinois Mathematics and Science Academyの創設者、Stephanie Pace Marshall
・書籍”Synchronicity”の著者で、リーダーシップ開発の権威であるJoseph Jaworski
・Genron Consultingの創設者の一人で、多様な人々からなるグループのデザイン、及びファシリテーションの権威であるAdam Kahane
・Society for Organizational Learningの創設者の一人で、米国、欧州、日本などでコンサルティングを手がけるClaus Otto Scharmer
・書籍”The Fifth Discipline”の著者であり、ラーニング・オーガニゼーションの提唱者であるPeter Senge
2. Concurrent Session
システム思考やラーニング・オーガニゼーションの考え方を実践・研究している各国の人々により、27のセッションが開催された
3. Clinic
今回のカンファレンスにおいても、例年同様、以下の2つのクリニックが開催されていた。
・Coaching Clinic
・Causal Loop Clinic
参加者の概要
今回のカンファレンスの参加者総数は約700名(うち日本人2名)であった。今回の参加者の特徴としては、前回弊社が参加した99年度と比べて、非営利団体や政府関係の参加者が増加していたことが挙げられる。特に米国の地域の教育団体が各州から参加しているのが目立った。また、海外の大学で組織開発やラーニング・オーガニゼーションの教育を行っている教授陣も数多く参加していた。
このように参加者のバックグラウンドが移行している背景としては、今後は、世界が経済よりも社会からより大きなインパクトを受けるという認知が広まり、社会を枠組みとする政府や団体、大学などが組織変革や教育の重要性をより高く感じ始めているということが仮説として考えられる。そういった中で、日本からは、企業のみならず、政府や非営利団体、大学からの参加者がないことから、我が国におけるラーニング・オーガニゼーションの認知度と問題意識は、まだまだ高いとは言い難いと感じられた。
カンファレンスの全体的な傾向及びテーマ
ホスピタリティ・スペースの醸成
高まるカンファレンスの盛り上がり
今回のカンファレンスの特徴の1つとして、例年と同程度に高い盛り上がりを見せていたことが挙げられる。他の国際カンファレンスでは、規模が縮小されたり、主催者・参加者のコミットメントが落ちつつある中で、システム・シンキングは、人数も700名を集め、運営もますますコミュニティ的に機能し、主催者・参加者のコミットメントも高まっている印象を受けた。また前回弊社が参加した99年のカンファレンスと比較しても、セッションにおける一体感、クオリティが向上していた。
このように、参加者の満足度が高く、活力に満ちたカンファレンスが維持できている理由の1つとして、共通のバリューを有した参加者が安心して自分の本音を語ることができ、探求やナレッジの創発が起きやすいような空間がカンファレンス全体を通して醸成されていることが挙げられる。この空間を象徴する言葉として、「ホスピタリティ・スペース」という言葉がカンファレンスの様々な場面で聞かれた。
ワールド・カフェ・コミュニティ
このようなホスピタリティ・スペースを構築するための基本となっているのが、「ワールド・カフェ・コミュニティ」と呼ばれる考え方である。
システム・シンキングのカンファレンスでは、例年ワールド・カフェ・メソドロジーと呼ばれる、組織においてコラボレーションやダイアログ、ナレッジのシェアなどをサポートする方法が取られている。具体的には、まず、セッションが行われる会場に、赤と白のクロスのテーブル掛けが敷かれ、中央に花瓶を置いた5人がけの小さなテーブルが用意されている。そしてあたかも町のカフェにいるかのようなリラックスできる雰囲気の中で、各テーブルに座った人々がダイナミックに他のテーブルへと移動を繰り返しながら、様々な人とダイアログを重ねていくということが行われていた。
この背景には、ナレッジとは、機能的な会議室の中で生まれるのではなく、人々がオープンに会話を行い、自由にネットワークを築くことのできるカフェのような空間でこそ創発されるという考え方がある。また、主催者によると、カフェ形式の会話の中で、参加者は、自分自身が「会話によって結びついている集合的知性の網の目の一部」であることを認識することができるとのことであった。
ラーニング・コミュニティが形成される条件や仕掛け
本カンファレンスのような、ナレッジの創発が起きるホスピタリティ・スペースを、自社組織の中に構築し、ラーニング・コミュニティを形成したいというニーズは現在日本においても高まってきているといえる。
しかしながら、オフィスにコーヒーを飲みながら会話が出来るコミュニケーション・スペースを設けたり、イントラネット上にバーチャルに議論ができるスペースを設けるなど、いわゆる箱を作るだけでは、うまくコミュニティが形成されないケースが多い。ラーニング・コミュニティを形成するには、入れ物を作ることに加えて、コミュニティを活性化させる条件が多く整備されていることや、触媒機能を果たす仕掛けが必要であると考えられる。
本カンファレンスが、コミュニティを形成するホスピタリティ・スペースとして機能している条件としては、以下のようなものがあったと考えられた。
探求の姿勢
参加者全員が、発言者の言うことをさえぎらずに熱心に聴き、そこから何かを探求しようという姿勢を持っている様子がありありと見受けられた。また、発言をするときは、「自分の意見が正しいんだ」といった断定的な話し方はなされずに、常に自分の意見はあくまで仮説として提示し、そこから本質を求めて深く掘り下げていくようなコミュニケーションが行われていた。
多様性の受け入れ
各国から集まった様々なバックグラウンドを持つ参加者の中で、既成観念やメンタルモデルを打ち壊すような、多様な意見、考え方が尊重されていた。具体的には、セッションの中で、それまでの議論の流れには出てこなかった別の観点を持った発言を行うと、例外意見として排除されるのではなく、暖かく拍手をもって迎えられていた。
学習へのコミット
参加者だけに限らず、運営側も含めてその場にいる人たち全員が、他者との相互作用を通して学習をするんだという雰囲気を作り出していた。特に、セッションの中でピアノ演奏を行うピアニストまでもが、セッションの途中で手を挙げ、質問をしたり、意見を述べていたのには驚かされた。また、カンファレンス事務局のコミットも高く、参加者のあらゆる質問に丁寧に応対したり、参加者同士のネットワーク形成を積極的に働きかけるなど、参加者が学習しやすい環境を構築するのに全力が尽くされていた。
リフレクティブな話し方
本カンファレンスの講演者、及び参加者の特徴として、自分が今何を考えているのかを一言ひとこと探っていくように、とてもゆっくりと話す姿が挙げられる。参加者の一人は、そのような話し方を称して「リフレクティブな話し方」と呼んでいたが、まさに自分の発言を通して、自身を回顧し、また相手にも回顧を促すような雰囲気を醸成していた。
また、コミュニティを活性化させる仕組みも多く設けられていた。以下にそのいくつかを紹介する
コミュニティ・ビルディング
カンファレンスが開催される前夜に、コミュニティ・ビルディングのセッションが特別に設けられていた。具体的には、自分が本カンファレンスに参加した目的や、カンファレンスを通じて得たいもの(新しい考え方やコンセプト、バリューといったInvisibleなものから、実践的なツール、スキル、ネットワークといったVisibleなものまで)が何かをまず振り返る。そして、自分と同じような目的を持つ人たちのコミュニティを作って、その中でお互いにアドバイスを与え合うなどのファシリテーションが行われていた。
セッションの内容の絵画化
基調講演においては、セッションの中で話されている内容が、リアルタイムでそのまま絵画的な物語として、模造紙に描写されていった。そのセッションの内容が描かれた模造紙は、カンファレンスの間中、常に会場の壁に貼られており、カンファレンスの会場自体が1つの物語の空間であるかのような雰囲気を生み出していた。そして、参加者は、自分が見たいときにその模造紙を振り返りながら、仲間とアイデアを共有することができた。
今後、ホスピタリティ・スペースを構築するためには、単に箱を作るにとどまらず、本カンファレンスに見られるようなコミュニティ活性化の条件や仕組みにはどのようなものがあるのかを把握し、それらを整備していくことが必要であると考えられる。
Leading in a Complex World(複雑な世界をリードする)
ダイアログ、及びリフレクションを通してのリーダーシップの探求
今回のカンファレンスでは、”Leading in a Complex World”(複雑な世界をリードする)というタイトルが、メインテーマとして挙げられおり、複雑で正解の見えない世界の中で、いかにリーダーシップを発揮していくかが、様々な切り口から探求されていた。
オープニング・セッションにおいては、リーダーシップを考える1つの材料として、英国人冒険家、アーネスト・ヘンリー・シャクルトンを題材とした演劇が行われた。シャクルトンは、南極大陸徒歩横断を成し遂げるために、エンデュランス号で南極に向かう途中、氷山の中で座礁するという極限状況の中、27名の人員を1人も欠くことなく、無事生還させた人物として知られている。近年リーダーシップの分野で、彼のリーダースタイルは注目を浴びている。本カンファレンスにおいても、厳しく、何が起こるかわからない厳冬の地で、部下と共に生き抜いたシャクルトンは”Leading in the Complex World”の象徴として、紹介されていた。
リーダーシップについて考えるにあたっては、主催者側から、特に明快なリーダー像が示されるわけではなく、上述したように、深い問いかけを通して、自分自身の考えを見つけていこうというスタイルが取られていた。セッションの中では、「リーダーシップの真髄は何だと思いますか?」「どのような状況が、自分自身がリーダーシップを発揮することを難しくチャレンジングなものにするでしょうか?」といったテーマのもとで、参加者間でのダイアログや、自分自身の考えについてリフレクションが行われていた。
今回のカンファレンスの特徴として、上述のように、ダイアログ、及びリフレクションの実践に最もフォーカスが置かれていたことが挙げられる。従来まで同カンファレンスの中で取り上げられてきたシステム思考やシェアドビジョンなどといったテーマと比較しても、ダイアログやリフレクションへのウェイトが高まっているように思えた。実際に行われていたセッションも、参加者同士が小さな輪になって、探求を行うダイアログ的なものが大半であった。またカンファレンスの合間には、これまで話し合われてきたテーマや、自分自身について、静かに振り返りを行う時間がいくつも設けられていた。多くのコンテンツを詰め込むのではなくて、本質的な課題をじっくり時間をかけて探求する姿勢が随所に見受けられた。
短絡的な質問から深い問いかけへ
このように、ダイアログやリフレクションにフォーカスが置かれていた背景には、「Deep Questioning(深い問いかけ)を行うことが、複雑な世界に生きるリーダーにとって重要な役割である」というカンファレンス全体を通しての1つの大きなメッセージがあった。
MIT教授であり、本カンファレンスのファシリテーターを務めたダニエル・キムは、次のようにコメントしている。「我々は現在の世界が複雑であることを体験をもって知っている。しかし我々は、得てして複雑な世界を単純なものとして扱ってしまう誘惑に駆られる。その結果、短絡的なアクションや解決策が導き出され、それ自身が問題を作り出しているのである。したがって、複雑な世界において、決断を下すためには、短絡的な質問ではなく、深い問いかけを行う必要がある。しかし、我々が何か重要な話をしようとすると、人々は決まってすぐ”どうやって?”という短絡的な質問をする。これらはいい質問ではない。このように単純に答えられるような質問をするために我々はわざわざこのカンファレンスに来ているのではないのである。」
このダニエル・キムのコメントのもと、本カンファレンスでは、短絡的な質問の代表として、次のような質問が提示されていた。
・How do you do it?(どのようにするのですか?)
・How long will it take?(どれくらい時間がかかりますか?)
・How much does it cost?(どれくらいコストがかかりますか?)
・How do you get those people to change?(どうやってこれらの人々を変化させますか?)
・How do you measure it?(それをどのように測るのですか?)
・How have other people done it successfully?(どのように他の人々はそれを成功させたのですか?)
ダニエル・キムは、これらの質問を「”How” Question」と呼び、本カンファレス内でこういった質問をすることを禁じた。
代わりに以下のような質問を深い問いかけの代表として提示され、これらの問いかけを通して内面的なリフレクションをすることが奨励されていた。
・What refusal have I been postponing?(どんな拒絶を私はこれまで延期してきましたか?仕事や生活において拒絶すべきことを延期していないでしょうか?)
・What commitment am I willing to pay?(どんなコミットメントを私は進んで行うでしょうか?)
・What is the price am I going to pay?(そのようなコミットメントをすることに対して、どんな対価を私は支払うでしょうか?)
・What is my contribution to the problem I am concerned with?(私が懸念を抱いている問題に対して、どんな貢献ができるでしょうか?)
・What is the crossroad at which I find myself at this point in my life/work?(私自身の生活や仕事において、私自身が交差点に立っていると感じるのはどこでしょうか?)
・What do you want to create together?(我々は何を一緒に作り上げたいのでしょうか?)
・What is the question that if you had the answer would set you free?(もし答えがあれば、自分を自由にしてくれる質問にはどのようなものがありますか?)
ここで提示されていた質問例の特徴としては、短絡的でなく、深い問いかけであることに加えて、多くの質問の主語が一人称の”I”(私)で始まっていることが挙げられる。そして、他人に深い気づきを促す質問を投げかけるよりも、自分自身の内面を振り返ることに重きが置かれている。
ここからは、リーダーシップのあり方が、他人に対してどう振舞うかという”How to Do”の観点から、自分自身がどうあるべきかという”How to Be”の観点へとシフトしていることが考えられる。”Be”の観点を重視する動きは今年度のASTDなどの他のカンファレンスでも見られており、リーダーシップの1つの傾向であるといえる。そして、自分自身の”Be”を深く問うために、リフレクション、及びDeep Questioningが重要視されている1つの要因であると考えられた。
ラーニング・サイクルを深くする
また、MIT教授で、ラーニング・オーガニゼーションの提唱者であるピーター・センゲは、彼の基調講演の中で、リーダーシップとラーニングの関係について述べていた。センゲは、ヒューレット・パッカード社のGMでSOL(Society of Organizational Learning)の初期のころからのメンバーであるグレッグ・マーティンの次のコメントを引用していた。「最も尊敬され、影響力、自信、そしてインパクトのあるリーダーは”Learner”(学習者)です。彼らは答えをもっていません。彼らは彼ら自身が答えをもっていないことを知っています。そして、彼らは本当の意味でリーダーの仕事は学習することであると信じています。よって、Learning Capability(学習能力)は、そのままLeadership Capability(リーダーシップ能力)に置き換えられるのです。」
現在の解の見えないComplex World(複雑な世界)においては、リーダーが明確な答えをもち、フォロアーがその答えに従うというスタイルをとることは不可能である。そこで、リーダー自身が学習者となって、常に問いかけを行い、ラーニング・サイクルを深くし続けていくことが、周囲の学習性を高め、それが効果的なリーダーシップにつながるというメッセージが伝えられていた。
ここで挙げられているラーニング・サイクルとは、図1に示す「Observe」→「Reflect」→「Invent」→「Produce」というジョン・デューイによって100年前に提唱されたものである。これは、観察し(Observe)、振り返りを行い(Reflect)、新しく可能なアクションを考え(Invent)、実際に行動を起こす(Produce)という基本的な学習のサイクルを指している。
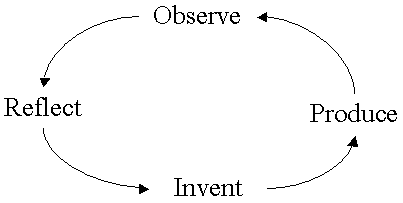 図1:ラーニング・サイクル
図1:ラーニング・サイクル
センゲはこのうち、Reflectの重要性を強調し、図2のように、リフレクションを深めることは、全てのラーニング・サイクルを深くすることに影響を与えると述べていた。
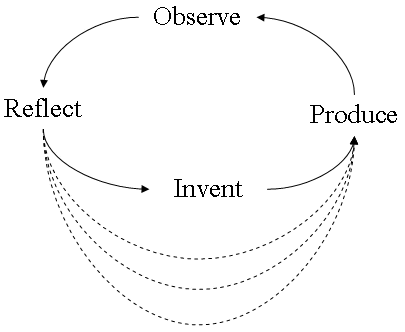 図2:ラーニング・サイクルを深くする
図2:ラーニング・サイクルを深くする
深いラーニング・サイクルが求められる背景
ラーニング・サイクルを深くしていくことが求められている背景について、MIT教授のオットー・シャーマーは、自らの調査に基づく、興味深い見解を述べていた。シャーマーは、医者と患者を対象としたインタビュー調査の中で、医者と患者の関係性を4つのレベルに分けた。
まず、一番表層の第1レベルは、Defect(欠陥)である。このレベルにおいては、医者は、患者の欠陥をただRepair(修理)するMechanic(メカニック)の役割を担う。つまり、患者が痛がっているところを薬などを使って対処療法的に直すことを指している。
次の第2レベルは、Behavior(行動)であり、これはDefect(欠陥)を生み出すもととなるものである。このレベルでは、医者はInstructor(インストラクター)としてTherapy(セラピー)を行い、患者の病気を生み出す行動や習慣を変えさせようとする。
次の第3レベルは、Thought(思考)である。このレベルにおいては、医者はCoach(コーチ)として、患者にReflection(リフレクション)させ、患者自身が自律的に考えや行動を改めていくよう促していく。
そして、一番深層にある第4レベルはSelf(自己変革)である。このレベルにおいては、医者は、Midwife for bringing forth the New(新しいものを生み出すことを支援する助産婦)として、患者自身が、自分自身がこうありたい姿を思い描き、それにむけてSelf-Transformation(自己変革)していくことを支援する役割を担っている。
シャーマーは調査の中で、医者、患者の双方に、自分自身が今いる現状の関係性はどのレベルにあるか、並びに、将来こうありたい関係性はどこにあるかを投票させた。すると、医者、患者ともども、現状では、レベル1、2にいるが、本当は、レベル3、4の関係性を望んでいることが判明した。また、これは必ずしも医者と患者の関係性のみに限らず、行政と市民、上司と部下、先生と生徒、農家と土壌など、全ての領域において、人間は深い関係性を求めていることが、調査により明らかになったとのことであった。
しかしながら、投票結果にもあるように、みなが下のレベルに行きたいにも関わらず、実際には行くことができていない。そこで、Self-Transformationのレベルに達するためには、リフレクションを行って、ラーニング・サイクルを深くし、「自分は何のために存在しているのか?」ということを問い続けていくことが必要であると述べられていた。
Presencing
ラーニング・サイクルを深くすることの重要性について先に述べたが、それではそのプロセスはどのようなものになるだろうか?この点について、オットー・シャーマーが、彼の提唱するコンセプト”Presencing”について講演を行っていた。
“Presencing”とは、2つの言葉を混ぜた造語である。1つは、”プリ・センシング”であり、これは「未来の可能性を、それが現れる前に嗅ぎ取る」ことである。もう1つは、”プレゼンス”であり、これは「現在」を意味している。シャーマーは、このコンセプトを通して、学習には以下に示した2つの異なるプロセスがあり、一般的に認知され、行われている1のプロセスに対して、2のプロセスは見過ごされていると指摘していた。
異なるラーニングのプロセス
1.Learning by the reflecting on the experience of the past ? act, observe, plan reflect, act -(過去の経験のリフレクションからの学習)
2.Learning from the future as it emerges(今現れようとしている未来からの学習)
そして、今現れようとしている未来から学習する”Presencing”を行うには、次のようなプロセスをたどることが必要であると説明されていた。
1.Downloading (reenacting habits)
現在自分がもっているメンタルモデルをダウンロードする。
2.Seeing (from outside)
古いメンタルモデルから脱却し、現在起きている出来事を外からありのままに見つめる。
3.Sensing (from the whole)
Seeingでは、自分自身を外部において、事象を観察していたが、Sensingの段階に
おいては、自分自身がその事象を構成するシステムの一部であることを理解し、自分自身の日々の行動がそのシステムにどういう影響を与えるのかを感じる。
4.Presencing (from the Source)
“Who is my Self?”、”What is my Work?” という根源的な問いかけを行う。ここでのSelfとは、”What is my future highest possibility?”(私がもつ将来の最高の可能性とは何でしょうか?)ということを指し、Workとは、”What am I here for”(私は何のためにここにいるのでしょうか?)ということを指す。
5.Crystallizing (from the future field)
6.Prototyping (from dialogic discovery)
7.Institutionalizing (from new practices)
リーダーシップの内面
今回のカンファレンスの大きなテーマは「複雑な世界におけるリーダーシップ」であったが、上述したシャーマーのPresencingのコンセプトのように、リーダーがリーダーシップを発揮する際にたどる内面的なプロセスが語られている場面が多かった。そして、リーダーについて考えるときには、リーダーはどうあるべきか、またはリーダーがどのように行動するのかという外見的なものではなく、内面的なプロセスや状態にフォーカスをシフトしていこうとする流れがあるとの印象を受けた。
