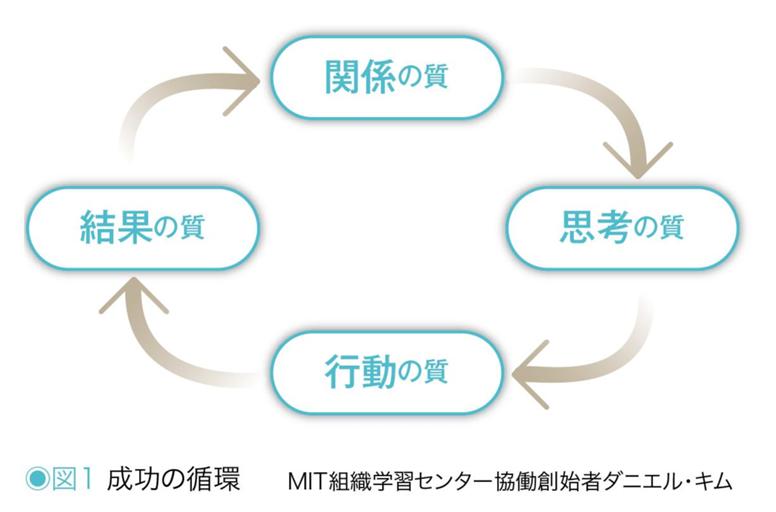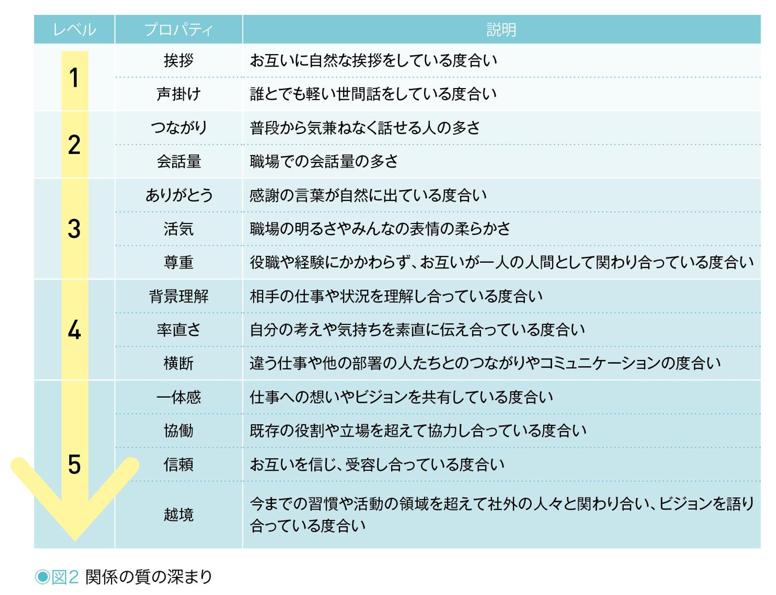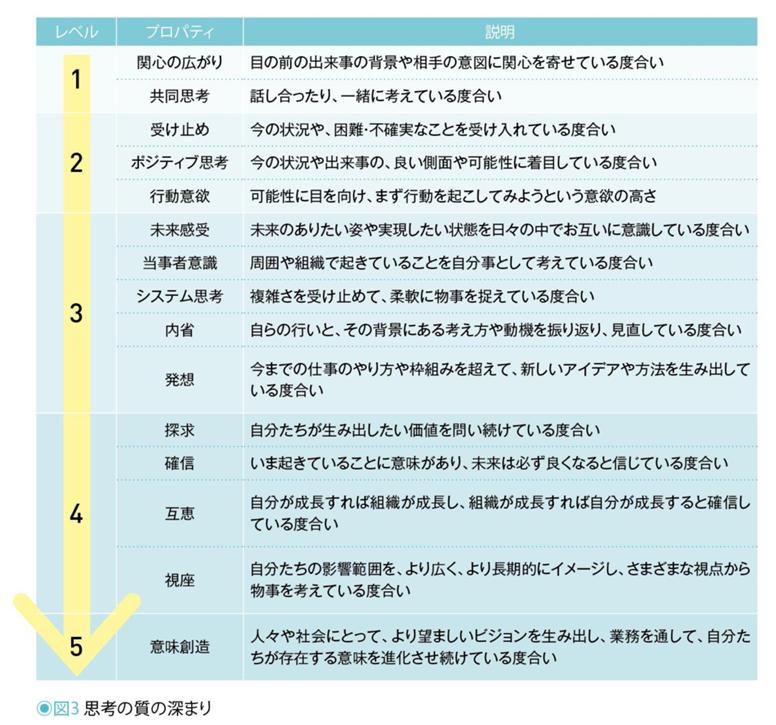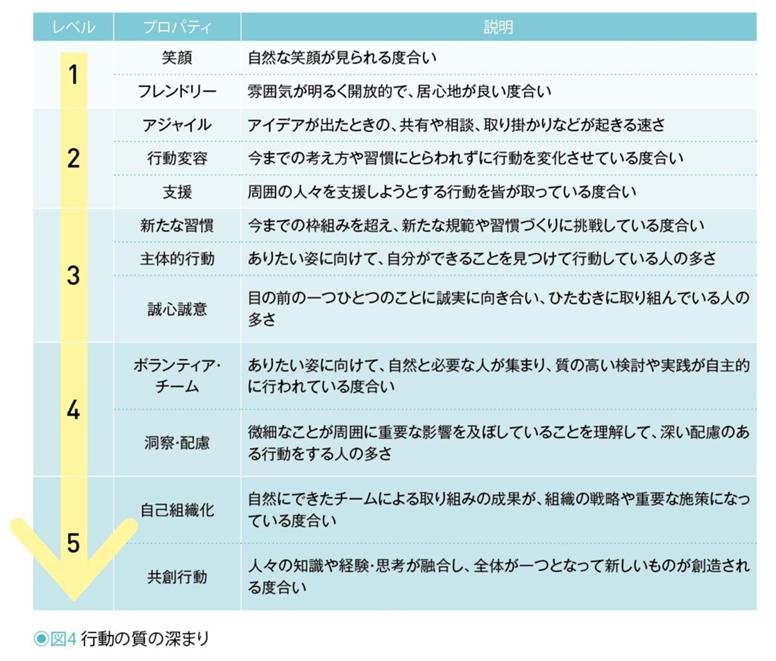株式会社ヒューマンバリュー プロセスガーデナー
清成勇一
2022年に入ってから、一般のニュースなどのメディアにおいても、Web3やNFT、メタバース、DAOというキーワードをよく耳にするようになりました。筆者は、「自律分散型組織」について調査・研究を進める中で、数年前から、DAO(ダオ)に着目していました。DAOとは「Decentralized Autonomous Organization」の略称で、日本語では「自律分散型組織」を意味します。このDAOは、中央集権ではなく、ブロックチェーンの技術を活用して自律的に情報を管理し、不特定多数がネットワーク上でつながりながら、目的の実現に向けて運営される組織体系を指します。海外での事例が多い中、日本国内でも実践している方の声を聞きたいという想いからリサーチしていたところ、この分野の第一線で実践されている岡 崇(おかたかし)さんとのご縁をいただきました。2018年11月に、社内の研究会にて、ブロックチェーンとDAOに関するトレンドや海外事例などをご紹介いただきながら、対話をする機会をもつことができました。そして、2022年に入り、Web3やメタバースなど国内でも注目が高まりつつある中で、あらためて、岡 崇さんに約4年間の実践を踏まえて、DAOの世界観や最新事例について、の会合で講演をいただきました。今回の会合の目的は以下の通りです。
・web3.0、DAO、メタバース、NFTなどのテクノロジーの最先端に触れる機会を通して、生物圏・人間圏・地球圏にいま加わった「バーチャル空間」の新たな可能性・あり方を探求するきっかけとなっている。
・DAOやweb3.0によって、人・組織のあり方にどのような変化がもたらされるのか。そこに向けて、私たちは何を受け入れ、手放し、そして何を大切にしながら歩む必要があるのか。対話する中で、そのポイントが浮かび上がっている。
・メタバースの世界に対応するための、心と身体の準備ができ、そこに向けて一歩歩めるようになっている。
本記事は、第1部で、での岡 崇さんの講演のサマリーや参加者の皆さんとのダイアログを紹介し、第2部では、私たちヒューマンバリューメンバーで対話したDAOと人・組織に関わる考察を共有いたします。