世界が、クローズシステムからオープンシステムに移行する今、狭い視野に陥った私たちの思考を解き放ち、より根本的な問題解決・イノベーションにつなげる「システムシンキング」は、これからのリーダーシップに不可欠なものです。
学習する組織を実現する「マネジャー育成」~メンバーの成長と成果向上を支援する~
マネジャーに求められる役割が大きく変わりつつある現在、ヒューマンバリューでは、「学習する組織」の考え方をマネジメントの実践に組み込んだマネジャー育成を行っています。
関連するキーワード
マネジャーのあり方の変化
マネジャーのあり方が大きく変化しています。指示命令や進捗管理といった従来の統制型のマネジメントでは、変化の激しい現在においてマネジャーとしてバリューを発揮することはできません。
メンバーの強みややりがいを伸ばし、ありたい姿に向けた主体的なチャレンジを支援し、成長・パフォーマンスの向上につなげていくようなピープル・マネジャーとしての役割が重要になっています。また、メンバーとの一対一の関係だけではなく、チームに活力と学習を生み出すチーム・マネジメントの側面も大切です。そこには、単にスキルやテクニックではなく、メンバーの成長を心から信じ、応援できるマネジャー自身のあり方(Being)も問われるようになってきています。
バリューを発揮できるマネジャーを育成する
今の時代に、マネジャーとしてバリューを発揮できる人材をどのように育成できるでしょうか? ヒューマンバリューでは、その指針に「学習する組織」の考え方を置いています。
マサチューセッツ工科大学のピーター・センゲ氏らによって提唱された「学習する組織」には、メンバー一人ひとりの想い・志を高め、相互に学習・協力し合いながら、皆で構造的な課題にチャレンジし、粘り強く成果を生み出し続けられるような組織・チームづくりのあり方が明示されています。
ヒューマンバリューでは、以下に示す学習する組織のディシプリン(規律)を日常のマネジメントに組み込むことによって、メンバーの成長と成果の向上を実現できるマネジャーを育成しています。
「学習する組織」を指向したマネジメント力を養うには
「学習する組織」づくりには、5つのディシプリン(規律)があります。
下記のポイントで紹介するように、この5つのディシプリンをマネジメントの実践に活かしていくことが重要です。
1.「自己マスタリー」:マネジャー自身の想い・志を高め、実践する
どんなに知識やスキルを学んでも、マネジャー自身のあり方が高まらなければ、周囲に影響を与えることはできません。
そこで、効果的なマネジメントを発揮するには、まずマネジャーとしての自分自身の想いや志、大切にしたい価値観を明らかにし、それを忠実に実践し、自己を研鑽する「自己マスタリー」が大切になってきます。
自分の想いや志を拠り所とすることで、難題に対しても、軸をぶらさずに向き合うことができます。
【実践のヒント(1):内省】
自己マスタリーは、外側から「あるべき姿」を与えたり、押しつけようとしてもうまくいきません。
本人が自分のこれまでの経験や未来のありたい姿を「内省」することを通して、自分が大切にしている想いや志、価値観を明らかにしていくことが重要です。
2.「共有ビジョン」:ありたい姿を描き、共有ビジョンを創造する
起きている問題ばかりに目を向けていると、対症療法を打ち続けることに陥り、エネルギーを失いがちです。
そこで、自分の想いや志に基づいて、自分が何を実現したいのかをありたい姿(ビジョン)として描くことが大切です。
そして、このビジョンを一人で描くのではなく、組織のすべての人々が共通して抱いているありたい姿を共有ビジョンとして描くことで、チームの力やエネルギーが高まります。
【実践のヒント(2):ビジョンを生きる】
共有ビジョンを創造する際に、マネジャー自身がビジョンを語ることはもちろん大切です。
しかし、それをメンバーに押しつけてしまうと、メンバーは受け身になってしまいます。そうではなく、マネジャー自身がビジョンを生きる(ありたい姿を実践する)ようになると、メンバーたちが自分のビジョンを考え始めます。
考え始めたら、皆で個人のビジョンを共有し、そこから共有ビジョンを生み出すことが重要となります。
3.「チーム学習」:メンバー同士の相互作用や学習性を高める
マネジャーが、より良いチームや組織を築いていくためには、メンバー一人ひとりに働きかけるだけではなく、全体に対して働きかけ、集団の相互作用や学習性を高めていくことが大切です。
メンバー同士が信頼し合える関係を築きながら、自己組織化的に課題解決を行えるような場づくりを行うことが必要です。
【実践のヒント(3):日常のミーティングや話し合いの機会を最大限に活用する】
集団の相互作用や自律性を高めるには、日常からコミュニケーションのあり方を丁寧に変えていくことが大切です。
一方的な説明や報告といったミーティングや会議のスタイルから、一人ひとりが考えたり、相互に学び合える話し合いになるように工夫しながらファシリテーションを行うことで、チームや組織の学習性が高まります。
4.「メンタルモデル」:仮説を保留し、探求する力を身につける
メンタルモデルとは、一人ひとりがもっている「思いこみ」や「固定観念」であり、個人や組織の思考、行動に強い影響を与えるものです。
自分たちが陥りがちなメンタルモデルを打破するためには、仮説を保留し、探求する力を組織的に身につけることが重要です。
【実践のヒント(4):対話(ダイアログ)のスキルを高める】
メンタルモデルは、一人で考えたり、同質性の高い人々で話し合っても気づきにくいものです。
組織内外の多様な視点から、探求を深めるためには、対話(ダイアログ)のスキルを高めることが不可欠です。
5.「システムシンキング」:構造的な問題に働きかける
目の前に見えている表面的な問題ばかりに目を向けて、対症療法を繰り返していると、長期的にはさらに問題が悪化し、ますます対症療法に依存するという悪循環に陥りがちです。
問題の背景にあるパターンや構造に目を向け、より根本的な問題に働きかけていくことが必要です。
そうした思考法は「システムシンキング」と呼ばれ、「学習する組織」を生み出す上で欠かせない考え方となっています。
【実践のヒント(5):原型の理解】
私たちはシステムシンキングの対極にある分析的思考に慣らされて育ち、仕事を進めてきたところがあるため、システム的、構造的な課題を理解し、働きかけることは、一般的にあまり得意ではなく、困難が伴います。
そこでシステムシンキングでは、典型的な課題のパターンを「システム原型」という形で類型化しています。
まずは原型を通して、自分たちの問題の捉え方を変えていくことが重要です。
「学習する組織」を指向したマネジャー育成の実践
ヒューマンバリューでは、15年以上に渡って、学習する組織、及び5つのディシプリンを一人ひとりがどのように身につけたり、組織の規律として確立していくかに関する研究と実践を重ねてきました。
そのアプローチにはニーズや状況に応じて様々なものがあります。たとえば、アクション・ラーニングやプロジェクトベースの取り組みといった長期間をかけて実践していくものもあれば、2~3日のマネジメント研修の中で5つのディシプリンを活かしていくものもあります。
昨今では、早期に大勢のチームリーダーやマネジャーを育成したいというニーズなどから、短い期間での学習機会を面的に設け、組織的にマネジメント力の向上を図ろうという動きも多くなってきています。
以下は、ある大手電機メーカーで、チームリーダー数百名を養成していく際に活用したプログラム例です。
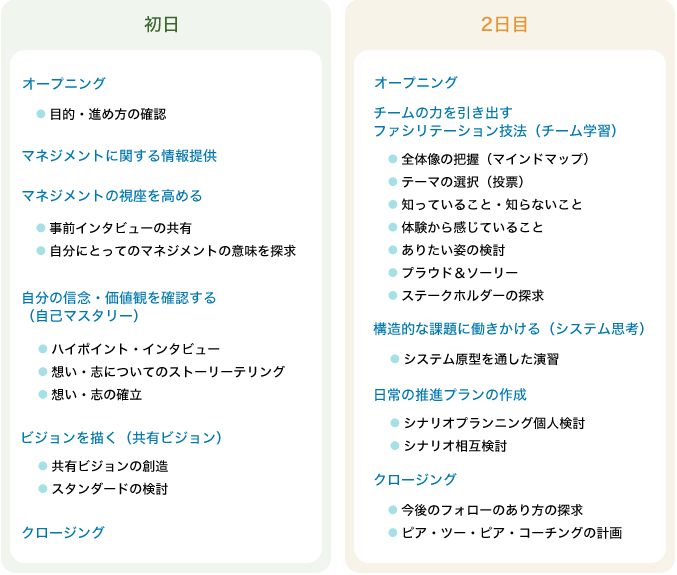
2日間の中で、自身のこれまでのマネジメント・スタイルを省みた上で、今後自分が学習する組織を築いていくために何が必要となり、それをどう高めていけばよいかのフレームワークを習得していきました。
また2日間のプログラムに加えて、レディネス(学習の準備態勢)を高める事前ワークの実施や実践のフォローなど、事前と事後のサポートを行うことで、主体的な学習の促進を併せて支援しました。
こうしたプログラムは、学習する組織が大切にしている哲学や原理を大切にしながら、より組織の状況やニーズに合わせたものにカスタマイズ開発しています。マネジメントに学習する組織の考え方を取り入れていくことに関心のある方は、お問い合わせください。
関連する取り組み
リーダーシップ開発
これからの時代のリーダーに必要なシステムシンキング
リーダーシップ開発
未来を切り拓く「リビングビジョン®」
メンバー一人ひとりの当事者意識と主体性を育む「リビングビジョン®」のプログラムは、企業におけるリーダーシップ開発やキャリア開発のあり方を大きく変革しています。ここでは、その取り組みを紹介します。
リーダーシップ開発
変革とイノベーションを生み出す リーダーシップ・ジャーニー®
ビジネスや社会の有り様が大きく変わってきている状況の中で、既存の枠組みを打破し、新たな価値を創出するような変革やイノベーションの必要性が、より一層高まっています。ヒューマンバリューでは、「リーダーシップ・ジャーニー®」と呼ぶ長期的なプロセスを通じて、イノベーションを自ら生み出せるリーダーシップの開発と組織の変革について、業界、業種を問わず支援しています。
関連するレポート
エンゲージメントは誰かが高めてくれるもの?<学習する組織ショート・コラム第6回>
2025.06.19インサイトレポート
本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。
バランス・スコア・カードが再び脚光を浴びる理由と課題<学習する組織ショート・コラム第5回>
2025.05.20インサイトレポート
本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。
インクルージョンは「同化」とどう違うのか?<学習する組織ショート・コラム第4回>
2025.04.02インサイトレポート
本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。
経営者に今投げかけたい問いは?<学習する組織ショート・コラム第3回>
2025.03.18インサイトレポート
本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。
「静かな退職」から「静かな成長」へ<学習する組織ショート・コラム第2回>
2025.03.04インサイトレポート
本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。
ビジョンは「浸透」させるもの?<学習する組織ショート・コラム第1回>
2025.02.13インサイトレポート
本連載では、学習する組織や組織開発の考え方や洞察をビジネスの文脈に照らし合わせて、短いコラムとして紹介しています。今後の組織づくりに役立つヒントやインスピレーションを得る機会となれば幸いです。
次世代リーダーシップ創造に向けたシステム思考学習の可能性〜東京都立日比谷高等学校における実践から考える〜
2024.11.05インサイトレポート
株式会社ヒューマンバリュー 主任研究員 川口 大輔 システム思考は、複雑な問題の本質を理解し、長期的な視野から変革やイノベーションを生み出していく考え方であり、社会課題にあふれた現代に生きる私たちに必須の思考法です。 ヒューマンバリューでは、これまで長年にわたりビジネスパーソンに対してシステム思考を広げる取り組みを行い続けてきましたが、今回、東京都立日比谷高等学校の生徒19名に対して、システム
編集後記:ビジネスパラダイムの革新に向けて、私たちにできること
2024.07.10インサイトレポート
ここまで5編にわたり、『GROW THE PIE』をお読みいただいた山口周氏のインタビューを掲載しました。ビジネスのあり方を考察し続けてきた山口さんとの対話は、日本企業の現在地をクリティカルに見つめ直す機会になり、GROW THE PIEの実践に向けて様々な気づきがありました。 最後に、編集後記として、インタビューの感想を交えながら、ビジネスパラダイムの革新に向けて私たちにできることは何か、現在
パイの拡大を導く、リーダーの思考様式と在り方とは(ビジネスパラダイムの再考 vol.5)
2024.07.10インサイトレポート
アレックス・エドマンズ氏の『GROW THE PIE』を読まれた独立研究家の山口周氏に、書籍の感想とともに、これからのビジネスパラダイムについてインタビューを行しました。(山口周氏 Interview Series) 本記事は、そのVol. 5となります。 今回は、パイの拡大や持続可能な社会の実現に向けて、企業リーダーにとって大切となる思考様式や在り方について語っていただきます。 Index
日本企業のパーパス経営を問い直す(ビジネスパラダイムの再考 vol.4)
2024.07.10インサイトレポート
アレックス・エドマンズ氏の『GROW THE PIE』を読まれた山口周氏に、書籍の感想とともに、これからのビジネスパラダイムを探究するインタビューを行いました。(山口周氏 Interview Series) 本記事は、そのVol. 4となります。 前回は、ビジネスにおけるヒューマニティの重要性を語っていただきました。 今回は「パーパス経営」を切り口にして、企業経営のあり方を考えていきます。
